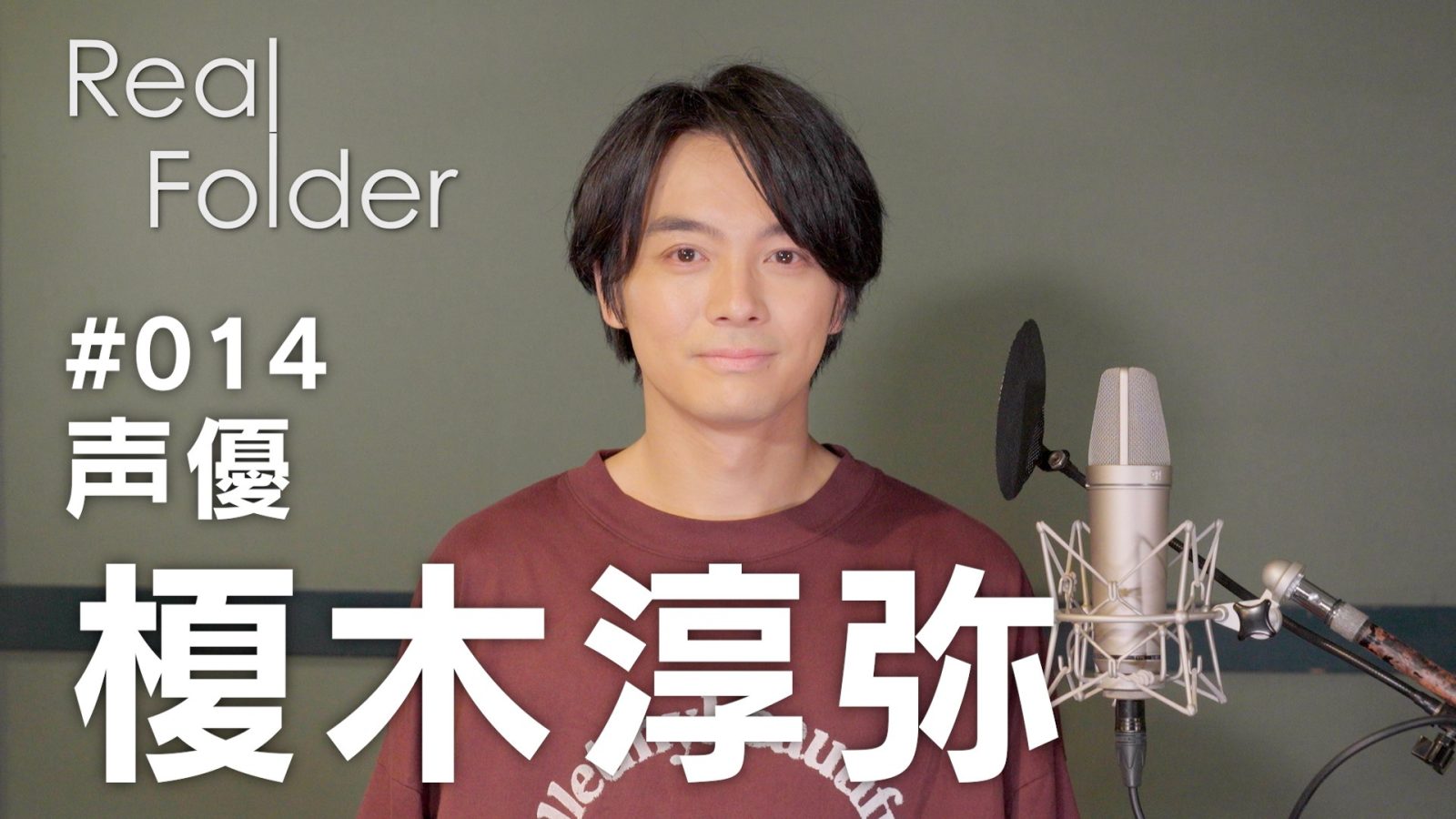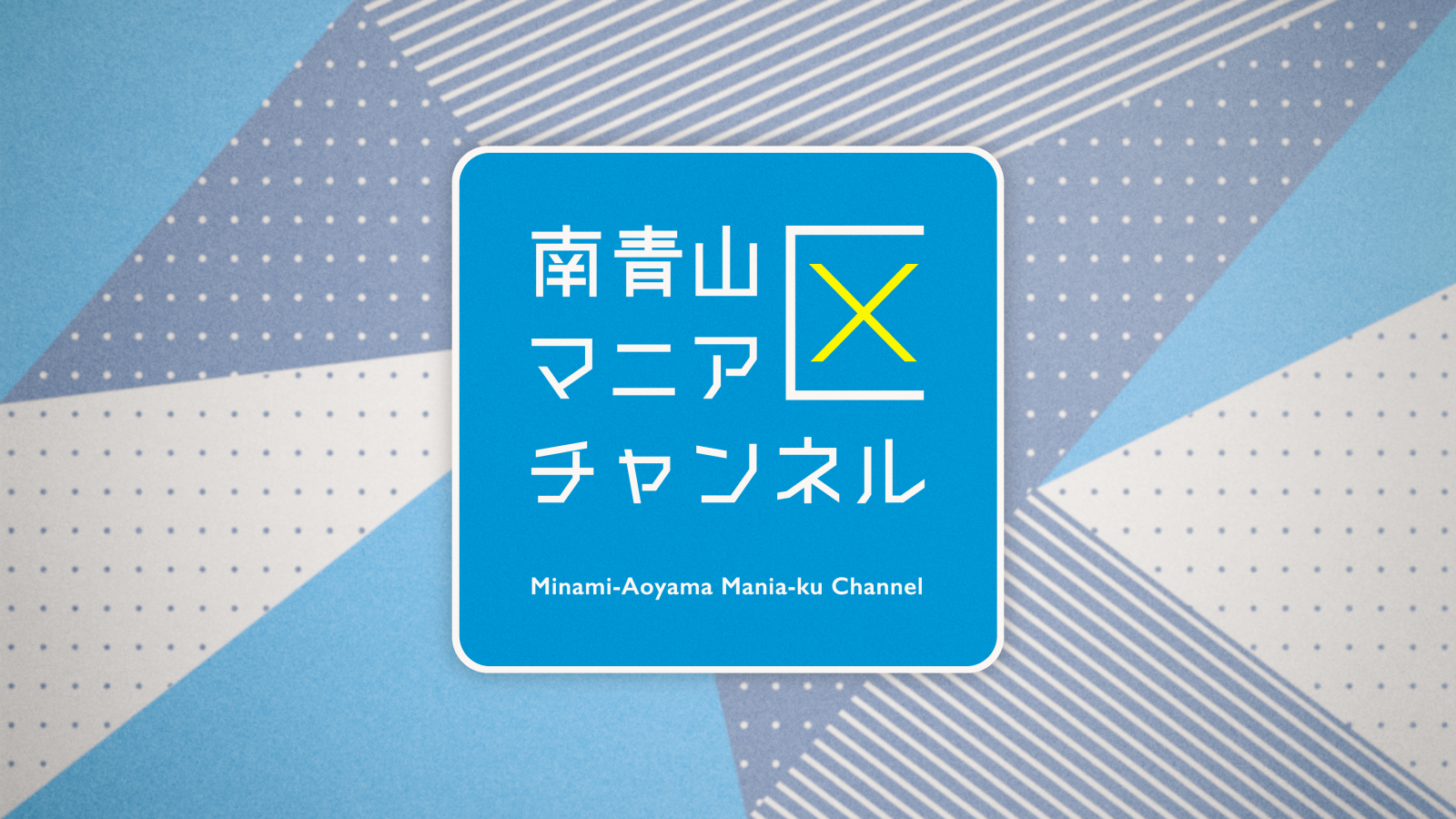VOICE MMJ社員のインタビュー

簡単に自己紹介をお願いします。
33歳ディレクターの大金です。フリーランスを経て、2023年4月に中途採用にて入社しました。
僕が所属しているネット配信・PR部は、ちょうど僕が入社した年度に新設されたセクションで、ドラマやドキュメンタリー・YouTubeやTikTok動画の企画演出・撮影・編集など、映像ジャンルや役職を問わず、所属部署の垣根を越えて活動しています。趣味はカメラ・写真・音楽鑑賞・路上観察です。
2024年9月に第一子男児が誕生し、3ヶ月間の育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)を取得しました。
育児休業を取得しようと思ったきっかけを教えてください。
特に具体的な事情があったわけではなく、もともと子どもが生まれたら一定期間は休業したいと考えていました。妻の仕事との兼ね合いや家事分担など家庭の都合ももちろんありますが、なにより「一生に一度しか見ることのできないわが子の "最初の成長" 」には父親として当然立ち会いたかったですし、その後の妻や子どもとの関係性にも直結する重要な時間だと思ったからです。
妻の妊娠がわかったのは2024年1月。その時点で僕はまだ入社1年目でしたので、自分が法的に休業できるのかどうか、会社の福利厚生はどうなっているのか、まずは自分で調べてみるところから始めました。そこで知ったのが、日本の育休制度−−−とりわけ父親に認められる育休期間が世界トップクラスだということ、そして国内男性の育休取得率が現状未だ2割にも満たないという、大きく矛盾した現実でした。何が原因でそうなっているのか知りたかったのも育休取得を決めた理由のひとつです。
今は職場復帰していますが、すでに息子の新生児期の生活が懐かしいです。(涙)

育休希望を伝えた際の上司・周囲の反応はどうでしたか?
僕が所属する部署は比較的フレキシブルに働けるということもあり、直属の上司や同僚には「おめでとう!気兼ねなくいってらっしゃい!!」と背中を押され引き継ぎ作業に移ることができました。職場に初めて相談したのは6月頃(出産3ヶ月前)でしたが、未経験の子育てや仕事との両立に漠然とした不安が出始めていた時期でもあったので、精神的にかなり救われました。休業申請のための手続きや給付金に関することも、管理部や経理部スタッフ・顧問社労士が中心となり、とても丁寧にサポートしてくださいました。
一方、先述の通り僕は所属部外の仕事も度々担当していますが、全てのスタッフから十分な理解を得るにはなかなか苦労したというのも事実です。育休に際し、当事者が気後れする必要は本来全くないはずなのですが、こればかりは実際に育休を取得した経験のある方でないと想像が及ばないだろうな…と実感しました。育児・介護休業法により雇用主側でも法整備が進んでいる現在においても、全社的にはなかなか浸透していないというのは弊社だけの問題ではない気もします。
現場レベルでの調整が思うように進まなかった過去を振り返ると、自分のキャリアへの不安や、仕事をカバーする同僚への罪悪感は少なからず感じてしまっていたかもしれません。これから子どもを授かり育休を望むスタッフが、気兼ねなく、当たり前に休業できる環境・雰囲気になることを心から願っていますし、育休を経験した僕自身がそのムーブメントのきっかけになれるなら、これほど嬉しいことはありません。
どれだけの期間、育休を取得しましたか?
子どもの生活リズムや離乳食が定着する時期、また育児休業給付金の給付率変動のタイミングなども考慮し、当初は6ヶ月を目安に希望していました。一時は2週間程の有給休暇を提案されたこともありましたが、それではただの「育児"体験期間"」に終わってしまう…。担当業務の都合もある中で上司数名と相談し、最終的には3ヶ月間の休業に決まりました。育休を頂けたこと自体はもちろんありがたかったのですが、生後3ヶ月を過ぎて子どもの寝返りが始まり、ミルクを卒業し、日中起きている時間が格段に増え、保育園入園までいっときも目を離せない未来が迫る中で、本当に大変なのはむしろこれから……というのが本音ではあります。光陰矢の如し…一瞬の3ヶ月間でした。
実際、育休を取得してみてどうでしたか?
育休中、妻とはざっくり時間帯で分担し、日中は妻が、夕方〜夜間は二人で、深夜〜翌日昼くらいまでは僕が担当するかたちで育児をしていました。授乳は1日約8回(昼夜関係なく3時間おき)。オムツは1日約8〜11枚消費。うんちの色も毎度チェックし、スマホの育児アプリに打ち込み夫婦間で共有。謎のギャン泣きでミルクが全く飲めず体重はどんどん減っていき、真夜中に#8000番(24時間365日電話がつながる子ども医療電話相談)にコールした日もありました。育休とは「仕事を"休"んで"育"児に徹する」期間である…と敢えて記しますが、自分の体を休める時間はほぼありません。映像のディレクターでありながらエンタメに触れられる時間も皆無。連ドラ観てる暇があるなら夫婦交代で数十分でも寝たい、然もなくば共倒れ…言わば育児ノイローゼ状態。個人差はあれど、仕事してたほうがよっぽど楽!!と身をもって感じました。それは妻も同じだったと思います。
育休を取得してよかったことを教えてください。
20時間超の陣痛から分娩まで立会い、新生児期の日々刻々と顔が変わる息子の成長を腕の中で見守ることができたのは、育休を取って一番良かったことだと思っています。今後子どもを何人持つかはわかりませんが、いずれにしても第一子である息子の「いま」は二度と見られませんし、「これから親になるんだ」という心の準備にここまで集中できたのは育休を取れたからに他なりません。
家庭内での実務的な部分は、正直妻と二人がかりでも一杯一杯でした。それでも夫婦揃って子育てに取り組むことで、うまくいかないというネガティブも含めあらゆる感情を共有できましたし、結果的に「今日は子どもを任せて出社できそうだ」とか「心身とも手一杯だから近くでサポートが必要そうだ」とか、職場復帰後も互いに気遣える信頼関係を築くことができていると思います。

復帰にあたり、不安に思っていたことはありますか?
全くなかった…といえば嘘になりますが(笑)、休業中も月に一度は所属部の定例会にリモート参加し近況報告させていただいていたので、復帰後に着手するプロジェクトの状況は事前に把握することができました。息子を抱えながら参加していたので、画面越しにみなさんとお話できたのも個人的に嬉しかったです。
また育休中に、区が実施している「赤ちゃん訪問」を夫婦で受けられたことも心の支えになりました。赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)とは、生後4ヶ月までの乳児をもつ全ての家庭を自治体の保健師等が訪問し、子育てや仕事に関する不安・悩みをヒアリングしてくれる市区町村主体の事業です。こういう場は得てして、出産した母親の産後ケアが主目的だと思っていたので、僕ともがっつり対話してくださったのは意外でした。新米の親として何かあったとき、どうにかなってしまいそうなとき、駆け込める寺は案外多いということ。そういう情報にいまアクセスできるということ…。とてもありがたいなと思います。
実際に復帰してみてどうでしたか?
おかげさまで、今のところスムーズに仕事復帰できているかと思います。日によっては上司から在宅業務を薦めていただけることもありますし、息子になにかあったとき、すぐ駆けつけられる環境で仕事ができるのは大事だな、と。休業前は想像していなかったですが、既にお子さんがいる先輩ママパパ社員との会話が増えたのも嬉しい一面です。「おさがりだけど〇〇要る?」とベビー用品を譲っていただいたり(笑)、心強いです。
仕事と育児の両立で工夫していることはありますか?
まだまだ完全体とはいえませんが、仕事における「効率化」と「コミュニケーション」のバランスを意識して働くようにはなりました。ディレクターとして、撮影やポスプロ(スタジオでの整音・編集作業等)時は現場に居ないと成立しませんが、個人で完結する事務作業やリモートで済む軽い打合せであれば在宅でも問題なく出来ています。また、何かの用事で出社した際は、居合わせた他の社員と少しでも雑談して帰るようにしています(もちろん相手の邪魔にならない程度にですが…笑)。極力フットワークを軽くしておき、妻の仕事復帰もできるよう考慮しながら、保育園入園まではなるべく息子のそばに居られたらと思っています。職種にもよりますが、フルタイムで在社していなくても多くの仕事が回ることはコロナ禍で証明されました。あとは、それによって陥りがちなコミュニケーションロスをどう工夫し解消するか。育児との両立に限ったことではありませんが、過去の古い勤務形態に固執せず、時代に合った風通しの良い働き方を模索することは、いまの仕事を次世代に繋ぐために重要なことだと思います。
男性でこれから育休を取ろうか考えている人へのメッセージをお願いします。
今回の育休を経て…。育児において、母乳をあげる等の一部を除き「ママにしかできないこと」は何一つない、ということを学びました。「イクメン」という言葉が流行り出して久しいですが、「育休とって子どもを育てる父親、偉いですね。」という空気はもはや一昔前の感覚で、女性も男性もみな等しく、もっと当たり前に子育てにコミットしてよいのだな、と。同時に、家庭における役割分担・パートナーシップのあり方は当事者内で決められるべき(本人同士が納得していれば、「夫は仕事・妻は育児」という従来の分担も肯定されるべき)、という想いも強くなりました。最も大事なことは、各家庭が望む子育てのカタチに対し、その家庭を囲む職場や地域がいかにして一体化し支援できるか…ということだと思います。
今年4月には新たな育児・介護休業改正法が施行され、また東京都では今年9月から、全国で初めて保育料無償化が第一子にも適用されるなど、僕たちが働きながら、より安心して子育てに取り組めるための施策を国や自治体は次々と打ち出しています。
これから初めて子育てを経験する人の多くは、入社10年未満の若手、もしくはこれから入社してくるZ世代の就活生たちです。結婚するもしないも、子を持つ持たないも自由な時代だからこそ、職場においても新しい世代の価値観やニーズを知り、あらゆる立場の人々が気持ちよく働ける環境を一人ひとり意識する必要があるのかな、とあらためて感じています。
僕自身、かけがえのない貴重な3ヶ月間を過ごすことができました。父親としてはまだまだ半人前ですが……育休を取得した一人として、新たな育休取得者が安心して休業・復職できる環境づくりを今後も考え、行動・発信していきたいと思っています。
写真:大金康平

2023年メディアミックス・ジャパン入社。
ディレクターとしてドキュメンタリー・ドラマ・YouTube作品などに携わる。